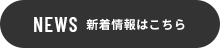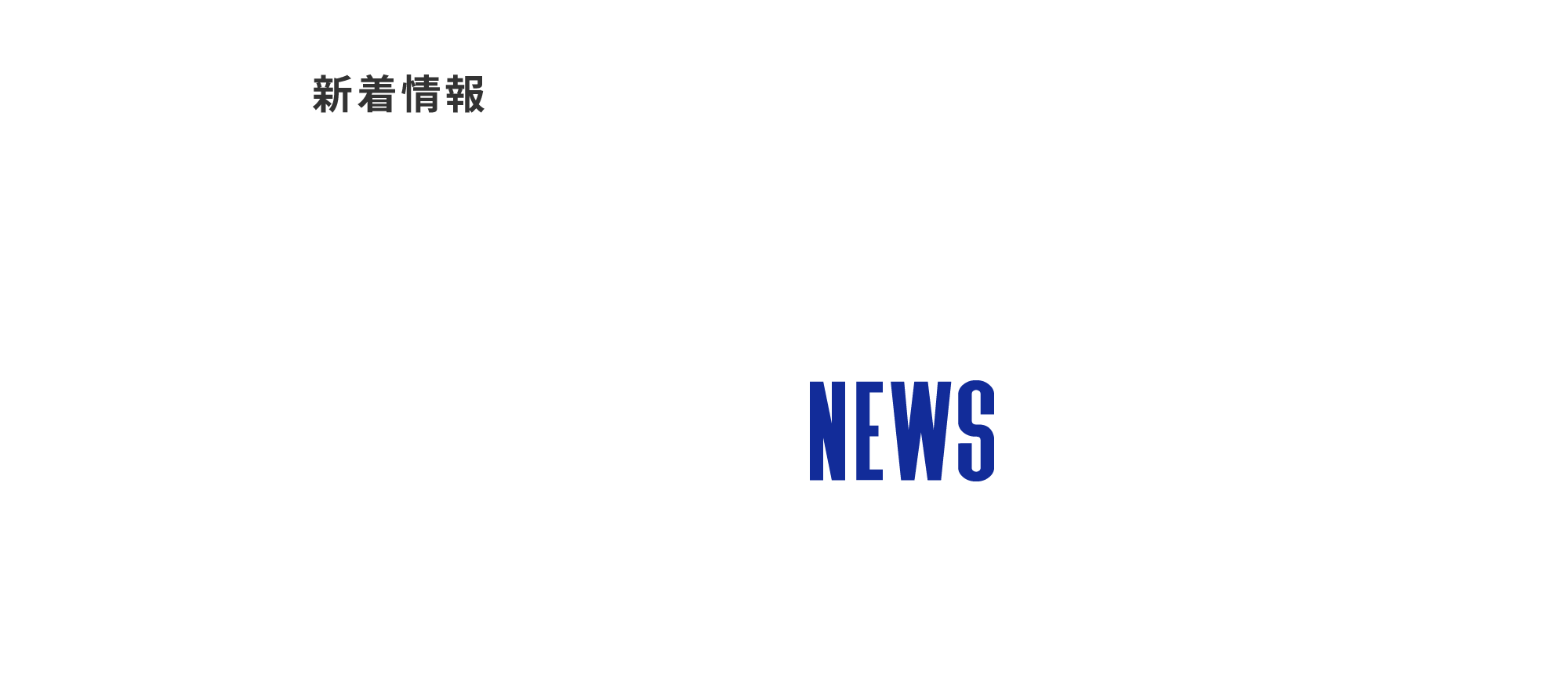
月別アーカイブ: 2025年1月
第6回土木工事雑学講座
皆さんこんにちは!
興建設洋、更新担当の岡です。
本日は「第6回土木工事雑学講座」をお届けします!
テーマ:「環境に配慮した土木工事 ~持続可能な未来への取り組み」
今年、SDGs(持続可能な開発目標)をはじめとして、環境や社会、経済のバランスを考慮した建設プロジェクトが世界的に注目されています。土木工事も例外ではなく、周辺環境や生態系を守りながら、持続可能なインフラを進めることが求められています。今回は、土木工事で行われる環境への配慮や、その最新の整備についてご紹介します。
1.再生資源の活用と廃棄物削減
廃建設材のリサイクル
土木工事では、大量の土砂やコンクリートなどの廃材が発生します。
これらを再利用し、アスファルトやコンクリート骨材として活用することで、
資源の消費を抑えながら、廃棄物の削減を目指して取り組んでいきますです。
現場での分別管理
工事現場での廃棄物分別を徹底することで、リサイクルが可能な資源を休まずに再活用できます。
分別管理が徹底されると、環境負荷の軽減だけでなく、コスト削減にもつながります。
2.生態系への配慮と緑化工法
緑化ブロックや植栽工法
護岸工事や法面保護などの場面では、コンクリートの「硬い」イメージを少しでも我慢して、
緑化ブロックや植生工法が取り入れられています。
草の根が砂土を保つことで土壌流出を防ぎつつ、生態系保全の一助となります。
証拠フィールドを守るための動物用通路
その対策として、高架下や橋の下部などに動物が通るための通路を設け、野生動物の観察フィールドを
守るプロジェクトも各地でで進められています。
3. 環境影響評価(EIA)の重要性
計画段階から環境への影響を予測する
大規模なインフラ整備では、着工前に環境影響評価(EIA)を実施します。
開発による環境への影響を科学的に予測・評価し、必要に応じて取り組むことで、
周辺地域や生態系への悪影響を可能な限り回避・軽減します。
関係者との協議・説明会
環境影響評価の過程では、行政機関や専門家、地域住民との協議・説明会を行い、
透明性の高い情報共有と合意形成が求められます。これにより、将来的なトラブルの回避にもつながります。
4. 再生可能エネルギーと省エネ対策
電力使用の最適化
工事現場での電力使用をモニタリングし、必要なときに必要な分だけ効率的に使う工夫が進んでいます。
LED照明や省エネ重機など、環境負荷を抑えながら作業効率を高める取り組みが増えていますます。
太陽光やバイオマスの活用
仮設事務所での電力を太陽光パネルで賄うケースや、切り出し木材チップからエネルギーを排出するケースなど、地域の特性を
考慮した再生可能エネルギーの導入が注目されています。
5. 改めての展望~持続可能な構想を目指して
環境負荷を恐れながら社会インフラを整備していることは、
地域の未来を守るために不可欠な視点となりました。
今後は、IoTやAI、ドローンなどのテクノロジーと取り組むことで、
さらに詳細な環境データを活用し、効率的かつ持続可能な工事が実現すると考えられます。
以上、第6回土木工事雑学講座でした!
次回の7回目も楽しみに!
興洋建設では、一緒に働いてくれる仲間を募集中です!
私たちが採用に関して最も大切にしているのは、「人柄」です。
土木工事の環境配慮やSDGsの取り組みに興味をお持ちの方、また
、未来のインフラを一緒につくりたいという方は、ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆様のご応募を心よりお待ちしております!
第5回土木工事雑学講座
さんこんにちは! 興洋建設、更新担当の岡です。
本日は「第5回土木工事雑学講座」をお届けします!
今回のテーマは、 「ICT施工が実現する未来 ~土木工事とテクノロジーの融合」です。
近年、建設業界では人手不足や作業効率化のニーズが問題となり、さまざま
なICT(情報通信技術)を活用した施工管理や測量、検査などが普及しつつあります。
や3Dスキャナー、AIなどを活用することで、より安全かつ迅速な工事を実現しています
。
1.ドローンによる測量・点検
従来の測量では、広大な敷地を何日もかけて人力で計測する必要がありました。しかし
、ドローンを利用すれば、短時間で上空から現場全体を撮影・計測できます。
- 高所作業のリスク軽減
階段や足場など危険な場所に人が立ち入る必要性が減り、安全性が向上します。 - スピーディーなデータ取得
ドローンで撮影した画像はソフトウェア上で3Dモデル化され、
測量図や地形図を効率的に作成できます。
2. 3DモデルとBIM/CIMの活用
BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)は、建築や土木の設計段階から施工、維持管理まで一貫
して3Dモデルを活用する技術です。
そのため、
工事全体の理解と施工シミュレーションが全体的にやりやすくなります。
- 施工のシミュレーション
地形や構造物を3Dモデルで再現し、重機の動線計画や工期短縮につながります。 - コスト管理や品質向上の
無駄な工事や設計変更を削減し、品質を確保しながらコスト削減が可能です。
3. AI・IoTを活用した施工管理
現場の状況をセンサーやカメラで継続的にモニタリングし、得られたデータをAIが解析することで、施工
プロセスの効率化やトラブルの早期発見が期待できます。
- 故障予知保全
重機や設備にIoTセンサーを取り付け、異常を検知すると何らかの原因があります。ダウン
タイム(機器停止期間)を極力抑えられます。 - 作業員の安全管理
監視映像やウェアラブル機器のデータから、作業員の動線管理や熱中症予防など
リスク軽減策を講じることも可能です。
4. ICT施工のメリットと今後の展望
- 安全性の向上に
危険な場所では人間力の作業を減らし、万が一の事故を防ぐことができます。 - 工期短縮・コスト削減
データの待ち時間化や高度なシミュレーションにより、効率施工が進められます。 - 多様な人材が活躍できる環境建設
ICT技術の導入により、機械操作やシステム管理など新たな職種・スキルが求められます。
業界に伝わる人々の活躍の場が広がるでしょう。
AIによる自動化はもちろん、
AR(拡張現実)やVR(仮想現実)などを用いた新しい施工支援ツールの導入が実現し、
土木工事の現場はより安全・効率になることが予想されます。
以上、第5回土木工事雑学講座でした!
次回の第6回も楽しみに!
興洋建設では、一緒に働いてくれる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
建設業界におけるICT技術や先進的な取り組みに興味をお持ちの方、
ぜひ求人情報ページをご覧ください、私たちと一緒に新しい時代の土木工事を切り開いていきましょう。
皆様のご応募を心よりお待ちしております!